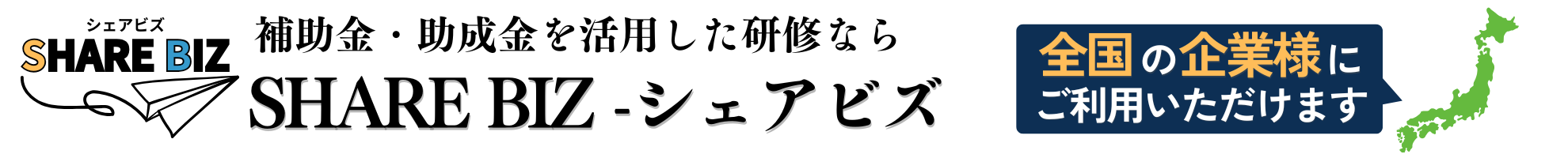テレワークの普及により、働き方の選択肢が増えるなか、「ワーケーション」や「プレジャー」という新たなスタイルに注目が集まっています。どちらも“仕事”と“休暇”を組み合わせた働き方ですが、その目的や取り入れ方には違いがあります。働きながらリフレッシュできる環境を整えることは、生産性の向上や人材確保にもつながります。本記事では、ワーケーションとプレジャーの違いや、導入するためのポイントについて解説します。
ワーケーションとは?
働きながら休暇を楽しむ新しいライフスタイル
ワーケーションとは、「ワーク(仕事)」と「バケーション(休暇)」を組み合わせた造語で、観光地やリゾートなど、普段とは異なる環境で仕事を行いながら、滞在先での観光や休息も楽しむ働き方です。
このスタイルは、仕事の合間に自然と触れ合うことでストレスを軽減し、業務効率や創造力の向上が期待できるとして、多くの企業が導入を検討しています。
プレジャーとは?
出張やビジネスの延長に“休暇”をプラスする考え方
プレジャー(Bleisure)は、「ビジネス(Business)」と「レジャー(Leisure)」を組み合わせた造語で、出張などのビジネス滞在に、個人の観光や休暇を付け加えるスタイルです。
たとえば、東京出張の後に1日延泊して観光を楽しむようなケースがこれにあたります。仕事の延長として自費でレジャーを組み合わせるのが特徴です。
ワーケーションとプレジャーの違い
| 比較項目 | ワーケーション | プレジャー |
|---|---|---|
| 開催の主目的 | 仕事と休暇を両立する | 出張業務に私的休暇を追加する |
| 実施の主体 | 本人の希望や企業主導での導入もある | 業務出張の延長として個人が計画する |
| 費用負担 | 企業が一部負担する場合もある | 休暇部分は個人が自己負担することが多い |
| 利用しやすさ | インフラが整った地域でないと難しい | 都市部など出張先で容易に実現可能 |
このように、両者は似ているようで目的や制度設計に違いがあり、それぞれの活用シーンに合わせて選ぶことが重要です。
ワーケーション導入のメリット
働く人と企業の双方に効果が期待できる
ワーケーションを導入することで、企業と従業員の双方に以下のようなメリットがあります。
- 従業員の心身のリフレッシュと生産性の向上
- 働き方の多様化による人材定着率の向上
- 地域との関係構築や地方創生への貢献
また、都市部から離れた地域での勤務は集中力を高めるきっかけとなり、リモートワークの延長として自然な形で取り入れることができます。
プレジャーのメリットと活用例
出張の効率を高め、個人の満足度も向上
プレジャーには、以下のような利点があります。
- 出張の移動費や滞在費を有効活用できる
- 短期間でも心のリフレッシュが可能
- 海外出張時には観光も楽しめて満足度が高まる
例えば「金曜まで出張し、土日に観光を追加して月曜に復帰する」といった活用方法は、私生活とのバランスもとりやすく、多くのビジネスパーソンに支持されています。
ワーケーションを取り入れる方法
導入には制度設計と設備の整備が不可欠
企業がワーケーション制度を導入するには、次のようなステップを踏む必要があります。
- テレワーク環境の整備(通信機器やセキュリティ対策)
- 勤怠管理のルール策定(労働時間や報告体制の明確化)
- 宿泊施設や地域との連携(地域の支援制度の活用も)
また、社員に任せきりにせず、試験導入として一部部署や短期間から始めることで、課題を見極めながら制度を成熟させることが可能です。
プレジャーを実践する際の注意点
公私の切り分けと労務管理がカギ
プレジャーを取り入れる際には、以下の点に注意が必要です。
- 公私の時間を明確に分け、休暇分は自費で賄う
- 勤務時間外の活動について会社と事前共有を行う
- 出張精算に私的活動費が含まれないようにする
これらを徹底することで、トラブルを未然に防ぎつつ、社員の柔軟な働き方を実現できます。
どちらを選ぶべきか?使い分けのヒント
ワーケーションとプレジャー、どちらを導入するべきかは、自社の業務内容や社員の働き方に応じて選ぶのが理想です。
- 長期滞在やプロジェクト型の仕事には「ワーケーション」
- 出張中心や短期利用には「プレジャー」
このように、仕事の性質に合ったスタイルを選ぶことで、より高い効果が期待できます。
まとめ
働き方の柔軟性が求められる今、ワーケーションやプレジャーのような新しいスタイルは、多くの企業にとって大きな可能性を秘めています。それぞれの違いを正しく理解し、自社に合った導入方法を検討することで、社員の満足度と生産性を同時に高めることが可能になります。
制度の導入には丁寧な準備とルール整備が欠かせません。まずは試験的に取り入れて、実際の効果を見ながら本格導入を進めていくのが成功への近道といえるでしょう。