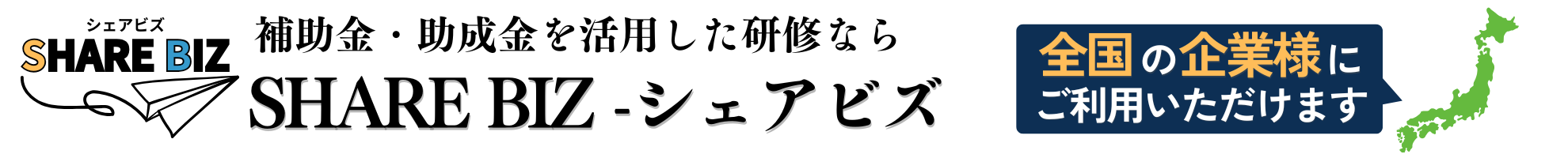採用活動を進める中で、一度は「内定を出したものの事情が変わって取り消したい」と考えたことがあるかもしれません。しかし、内定を出すという行為には法的な意味合いがあり、安易な取り消しは企業側に大きなリスクをもたらします。この記事では、内定の法的性質や内定取り消しが認められる条件、企業が注意すべきポイントについて詳しく解説します。
内定とは何か?その法的な意味
採用内定は「始期付き・解約権留保付きの労働契約」
一般に「内定」と呼ばれるものは、実際には労働契約の一種です。内定通知書を交付し、求職者がこれを承諾した時点で、法律的には「雇用契約が成立している」と見なされるケースがほとんどです。
この労働契約は、内定者が入社予定日から勤務を開始することを条件とした「始期付き契約」であり、企業側には合理的理由があれば契約を解除できる「解約権」が留保されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約の性質 | 労働契約(始期付き・解約権留保付き) |
| 効力発生の時期 | 通知書の交付と承諾が完了した時点 |
| 取消の可否 | 合理的理由がないと無効とされる可能性がある |
内定取り消しはどんな場合に認められるのか?
客観的に正当な理由がある場合のみ
企業が一方的に内定を取り消すことは、法律上「解雇」に近い性質を持ちます。したがって、解雇と同様に客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。
以下のようなケースでは、内定取り消しが有効と判断される可能性があります。
- 内定者が経歴を詐称していた
- 入社までに重大な犯罪行為を行った
- 入社不可能な健康上の問題が発覚した
- 会社の経営状態が急変し、雇用継続が不可能となった
ただし、いずれも十分な証拠と事前の説明がなければ、無効と判断されるリスクがあります。
不当な理由による取消しは違法になる
以下のような理由での内定取消しは、労働契約法や民法に反するとされ、損害賠償の対象になる可能性があります。
- 単に採用枠が変わった
- 上司の一存でキャンセルされた
- 性別や年齢、出身校など差別的な理由
このような取り消しがトラブルに発展すると、企業の社会的信用を失うだけでなく、損害賠償請求や訴訟対応などの負担も発生します。
内定取り消しを行う際の注意点
十分な説明責任と手続きが不可欠
内定取り消しを行う際は、内定者本人への丁寧な説明が必要です。さらに以下のような手順を踏むことが望ましいです。
- 取り消し理由を文書で明示する
- 本人との面談を設け、納得を得る努力をする
- 必要に応じて代替案や補償を検討する
企業側の誠意ある対応が、のちの法的リスクの低減にもつながります。
内定通知前に「選考中である」ことを明確に
内定通知前の段階では、選考が継続中である旨を明確に伝えておくことで、誤解を避けることができます。とくにメールや電話口でのやり取りには注意が必要です。
以下のような記載が推奨されます。
- 「最終面接後に内定の有無をご連絡します」
- 「選考は継続中であり、確定ではありません」
曖昧な表現で内定を仄めかすことがないよう、社内教育を徹底しましょう。
トラブルを防ぐために企業がすべきこと
採用基準と選考プロセスの明文化
内定取り消しリスクを防ぐには、まず採用基準やプロセスを明確に整備し、関係者間で共有しておくことが重要です。
- 書類審査から内定通知までの流れを標準化
- 内定通知書に法的な留意事項を記載
- 入社予定者に対して社内ルールを事前に共有
これにより、感覚的な判断での内定や取消しを防ぐことができます。
| 企業が整備すべき内容 | 目的 |
|---|---|
| 採用フローのマニュアル | 法的手続きの遵守と判断基準の統一 |
| 通知書のテンプレート | トラブル防止と契約内容の明確化 |
まとめ
内定とは単なる約束ではなく、法律上はすでに労働契約が成立している状態です。企業が一方的に取り消すには、合理的な理由と社会的妥当性が求められ、軽率な対応は重大なリスクを招きます。
採用活動においては、内定を出す前後の対応を慎重に行い、文書化・説明責任・情報共有を徹底することが、トラブル防止と企業価値の維持につながります。